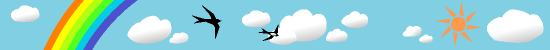
水の科学・化学館④
「水」をとりまくものは、限りなく果てしない。その外郭を探ってみる。
気象学 きしょうがく Meteorology
地球の大気、およびその中でおきる現象について研究する学問分野の総称。
大気中にはさまざまな自然現象がある。 そのため気象学は、次のような、いろいろな研究分野にわかれている。
総観気象学は日々の天気の変化を研究する。
物理気象学は、雷などの電気現象、虹(にじ)や蜃気楼(しんきろう)などの光学現象、可視光線や赤外線などの放射による 大気の加熱・冷却の仕組みを研究する。
気候学は、大気の平均状態や地域的な気候の変化、長い期間にわたる気候の変化を研究する。
微気象学は、地面付近のせまい地域の風や気温の変化を研究する。
高層気象学は、成層圏やそれよりももっと高層の大気を研究する。
そのほかにも、雲物理学、気象力学、局地気象など、さまざまな研究分野がある。
気象観測の歴史
前4世紀ごろ、古代ギリシアの哲学者アリストテレスは「気象学Meteorologica」を書き 「上空にあるものについての研究」をおこなった。 その多くは気候誌的記載である。英語のmeteorologyは、アリストテレスの本の題名に由来している。
科学研究の歴史をみると、物理学や化学の法則の発見は、大気現象に対する興味がきっかけになっていることが少なくない。
人々は古くから天気予報をこころみてきた。 経験的な天気予報の知識は、天気俚諺(りげん)や天気暦(てんきれき)としてまとめられ、後世にうけつがれてきた。 天気俚諺とは、「夕焼けは晴、朝焼けは雨」というような天気についての経験的な言い習わしのことである。 しかし、科学的な天気予報の研究がはじまったのは、19世紀に熱力学や流体力学の基礎理論が確立したあとのことである。
気象観測の発展も気象学の進歩にかかせないものである。 新しい気象観測装置の開発や気象観測網の充実が、気象学の発展に大きく貢献している。 14世紀には、すでに気象観測をおこなった記録があるが、組織的な気象観測は17世紀になってからである。 当時、現在のように通信手段がととのっていなかったことも、気象学の発展をさまたげた。
19世紀の中ごろ電信が発明されると、ひろい範囲で観測した気象のデータが短時間のうちに1つの場所にあつめられ それらのデータをもちいて天気図をかくことができるようになった。
気象学については第1次世界大戦のころにはさらに近代化された。その推進力となったのは、ノルウェーの気象学者たちである。 ビャークネスを中心としたベルゲン大学のグループは、中緯度の天気の変化の原因となる温帯低気圧(低気圧)が、寒気団と 暖気団のぶつかりあう場所で発生することを発見し、その場所に「前線」という名前をつけた。 現在の天気図でつかわれる寒冷前線や温暖前線という言葉も、ビャークネスがはじめてつかった言葉である。 ビャークネスの時代には、地上の気象観測しかできなかったが、その後、後述するレーウィンゾンデが発明され 上空の大気の状態を観測できるようになった。
第1次世界大戦がおわった直後、イギリスの数理物理学者で気象学者でもあったルイス・リチャードソンが、物理法則を つかって天気を予報する方法を提案した。この方法を「数値予報」という。 彼の時代にはコンピューターがなかったために、数値予報は実用にならなかった。 しかし、第2次世界大戦後、コンピューターの驚異的な発展によって、現在では数値予報が実用化され、日本をふくむ 多くの国の天気予報は数値予報によっておこなわれている。
気象観測
第2次世界大戦中から戦後にかけて、上空の風を観測する方法が進歩し、天気予報の考え方を一変させた。
それまでは、地上気象観測データをあつめてかかれた地上天気図が、天気予報のよりどころになっていたが、上層の 大気の流れに着目する方法に変化した。それと同時に、地球規模の大気の流れ(大気大循環)に対するイメージもかわった。
新しい大気大循環の研究にもっとも貢献したのは、スウェーデン生まれでアメリカで研究をつづけたC.G.ロスビーと彼の 仲間である。彼らは、第2次世界大戦中に発見されたジェット気流の仕組みを研究した。 ジェット気流とは、北半球と南半球の中緯度の大気の上空10km程度をふく強い西寄りの風のことである。
1950年になると、物理学や熱力学の法則をあらわす数式をコンピューターで計算し、大気循環のようすを再現できるようになった。 それが天気予報に応用されたものが数値予報である。現在では、数値予報は一般の天気予報ばかりでなく、産業や 農業の分野でも利用されている。
地上気象観測
現在では、高層気象観測よりもはるかに高い密度で、地上気象観測がおこなわれている。
地上気象観測の項目としては、気圧、気温、湿度、風向風速、雲量、視程(遠くを見とおせる距離)、降水量である。
降水量とは、雨量または降雪量のことをさす。雨量とは、雨水がふった場所からながれださないで、その場にたまったと 仮定したときの深さをmmの単位であらわしたもの。
降雪量とは、雪がその場でとけて液体になった場合の深さをmmの単位であらわしたもの。
雪がふわふわした状態でつもっている高さは積雪量という。
気圧測定の基準となる測器は水銀気圧計である。しかしもちはこびに不便なので、船上での観測や気圧の時間的な変化を 知るための自記気圧計(バログラフ)として、測定の精度はおちても、より簡便なアネロイド気圧計がもちいられる。 気圧計は、気温によって影響をうけるので、正確な測定をおこなう際には気温による影響の補正をおこなう必要がある。 また、測定する高度によって気圧は変化するから、地上天気図の等圧線をかくためには、測定点の高度の影響を考慮し 海面で測定したと同じ値に補正する必要がある。この補正を「気圧の海面更正」という。
温度をはかる方法はいろいろあるが、気象観測の目的には、普通の水銀またはアルコール温度計でじゅうぶんである。 しかし、ただしい気温をはかるためには、昼間は温度計の感部に日射が直接あたらないように注意する必要がある。 また、夜間に感部を野外にだしておくと、放射冷却で感部だけがひえ、ただしい気温を測定できないことがある。
大気中にふくまれている水蒸気の量は湿度計で測定する。もっともよくつかわれる湿度計は乾湿球湿度計である。 これは、2本の温度計を左右にならべたもので、片方は気温を測定する。 もう片方はしめったガーゼをまいた状態で気温を測定する。前者ではかった気温を乾球温度、後者ではかった気温を 湿球温度という。ガーゼから水が蒸発する際に熱をうばうので、湿球温度のほうが、乾球温度(気温にひとしい)より低くなる 乾球温度との差はその場の湿度によるので、その差と気温から湿度をもとめることができる。
ある種の物質の電気抵抗が湿度によって変化する性質を利用した、電気抵抗湿度計も開発されている。 この原理による湿度計はラジオゾンデに搭載され、高層気象観測につかわれる。
風の観測には、風向きと風の強さの両方の観測が必要である。 風向きだけをはかる装置を風向計、風の強さをはかる装置を風速計という。 風向きと風の強さを同時にはかることのできる装置を風向風速計という。 プロペラと垂直尾翼しかない飛行機のような形の風向風速計がつかわれることがある。 これは胴体が軸に固定されており、風がふくと、つねにプロペラが風にむくようにできている。 その向きから風向(風のふいてくる方向)がわかる。また、プロペラの回転数から風速がわかる。
降水量は、雨量計または降雪計ではかる。雨量計は、口のひらいた円筒形の筒で、その中に雨をため、底にたまった雨水 の深さ(単位はmm)で雨量をしめす。 降雪計は、やはり口のひらいた円筒計の筒であるが、雪をとかす装置がくみこんであり、底にたまった雪解け水の深さを 雨量と同じ方法で測定する。
積雪は、地面につもった雪のあつさのことである。地面に垂直にたてた物差しで積雪を測定する。
気象観測装置の中には、対象物に直接ふれないで測定するものもある。一般にリモートセンシング(遠隔測定)という。 もっともよくつかわれるリモートセンシングは、気象レーダーである。 気象レーダーは、空中の雨や雪から反射してくる電波をとらえて、数百キロメートルの範囲の雨や雪のふっている場所の 分布を知る装置である。この装置によって、台風、竜巻、集中豪雨などの位置がわかる。
このほかのリモートセンシングとしては、雲底の高さをはかるシーロメーター、大気の透明度をはかる視程計がある。 シーロメーターや視程計による観測は、飛行機の離着陸に重要なため、飛行場でおこなわれることが多い。
高層気象観測
上空の大気の状態を定量的に知ることは、天気予報のためにも、また、航空の安全のためにも必要である。
現在では、定期的な高層気象観測が世界各国でおこなわれている。 各国の気象台では、グリニジ平均時の0時と12時、日本時間の午前9時と午後9時にいっせいにレーウィンゾンデを放球して 上空の大気の状態を観測することになっている。
レーウィンゾンデとは、上空の風向風速を測定できるラジオゾンデのことである。 ラジオゾンデは、上空の気圧、気温、湿度を測定する気象測器である。 この計器を15cm四方ほどの箱の中にいれ、ヘリウムのはいった直径1mほどの気球にぶらさげて放球する。 ラジオゾンデは一定の速度(およそ5m/秒)で上昇しながら、気圧、気温、湿度を測定する。 測定したデータは、ただちに電波で地上局におくられてくる。
風向風速を測定するには、ラジオゾンデの位置が時々刻々わかればよい。 ふつう、位置を知るために、地上に設置された電波探知機でラジオゾンデから発信される電波をとらえ、方向を測定する。 ラジオゾンデの上昇速度が一定であれば、計算によって、ラジオゾンデの位置を知ることができる。 しかし、ゆれる船の上では、ラジオゾンデの方向を知ることがむずかしい。 そこで、ラジオゾンデ自体が自らの位置を受信局に知らせてくるタイプのゾンデも開発されている。 自らの位置を知るためには、地上や人工衛星から発信される電波を利用する。 地上局を利用する場合を「オメガゾンデ」、人工衛星を利用する場合を「GPSゾンデ」という。
飛行機も気象観測につかわれるが、最近は、定期的な観測よりも研究のためにもちいられることが多い。 10年ほど前までは、海上で台風の観測をおこなうため、グアム島を基地にしてアメリカ軍の偵察飛行がおこなわれていた。 しかし、静止気象衛星「ひまわり」の雲画像で台風の位置や強さがある程度わかるので、現在は、台風観測のための 偵察飛行はおこなわれていない。
今日、人工衛星は、さまざまな用途にもちいられているが、気象観測にも大きな威力を発揮している。 気象観測にもちいられる気象衛星は、軌道衛星と静止衛星の2種類に分類される。
軌道衛星は、地球表面のあらゆる場所を通過できるように、北極と南極の近くをとおる軌道をえがくようにうちあげられる ので、極軌道衛星ともいう。現在、アメリカの衛星「ノア」が活躍している。 830kmの高度を101分の周期でまわりながら雲の分布を観測し、可視光線と赤外線でとらえた雲の画像を電波で地上におくっ てくる。日中は可視光線だが、夜間は赤外線の画像のみがおくられてくる。水平の分解能は約800m。
これに対して静止気象衛星は、赤道上の約3万6000kmの高度にうちあげられ、東向きに24時間の周期で地球を一周する。 地球も24時間の周期で自転しているので、地球上からみると、人工衛星は静止しているようにみえる。 現在、赤道上を5個の静止気象衛星がまわっている。日本の静止気象衛星はGMS(愛称「ひまわり」)とよばれ、1977年(昭和52) に気象庁がうちあげて以来、1時間ごとに、裏側はみえないが地球全体の雲画像を地上におくってくる。 95年3月に「ひまわり」5号がうちあげられ稼働中である。その画像は、毎日の天気予報や台風の進路予報に利用されている。 可視画像の分解能は1〜2km、赤外画像は約5kmである。
天気予報には上空の気圧や気温の情報が必要であるが、気象衛星でそれらを観測することは、現在の技術ではまだできない。 そこで、気圧計や温度計を搭載した気球を上空にあげ、つねに一定の高度をただよいながら気象観測をおこなおうという 実験がおこなわれた。この技術をGHOST(ゴースト)という。GHOSTとは、Global Horizontal Sounding Techniqueの頭文字を とったものである。しかし、たくさんの気球を同じような間隔で配置しても、時間がたつうちに間隔に粗密ができてくるので 現在はまだ実用化されていない。
地球大気の循環
風がふく原因は、太陽放射による大気の加熱が場所によってことなることである。
地球規模でみれば、南極や北極の付近にくらべて赤道付近は日射量が多く、強く加熱される。 そのために、緯度によって気温の差が生じる。この差を小さくするように、地球規模の大気循環(大気大循環)が生じるのである。
したがって、大気大循環は熱を低緯度地域から高緯度地域にはこぶ一種の熱の対流である。 大気大循環は、低緯度のハドリー循環と中高緯度のロスビー循環にわかれている。 ハドリー循環とは、赤道の近くの緯度帯で空気が上昇し、その両わきの、北半球と南半球のそれぞれ緯度30度程度まで ひろがる緯度帯で空気が下降し、下層でまた赤道の方向にむかう循環である。
空気が下降する範囲を亜熱帯高圧帯という。 地表面付近で空気が赤道にむかうとき、コリオリの力の作用で東寄りの風(東から西にむかう風)になる。 この風を貿易風という。北半球の貿易風と南半球の貿易風は、赤道の近くでぶつかりあい、そこで上昇する。 その緯度帯を熱帯収束帯という。そこは風が弱いので、赤道無風帯(ドルドラム)ということもある。 熱帯の地表面のひろい範囲は海面なので、そこからたえず水蒸気が蒸発しており、それに接した空気は水蒸気をたっぷり 供給される。その水蒸気は、空気が熱帯収束帯で上昇すると、上空で凝結して雲になり、しばしば巨大な積乱雲になるまで 発達して、多量の雨をふらせる。「ひまわり」の雲画像をみると、赤道付近に雲が多いのは、そのためである。 熱帯収束帯で上昇した空気の一部は北半球にむかい、亜熱帯高圧帯で徐々に下降する。 そこでは雲は発達しにくいので、「ひまわり」の画像では黒くみえる。その下に陸地があると、雨がほとんどふらないために 砂漠になる。アフリカのサハラ砂漠や、オーストラリアの砂漠はその例である。
また、ハドレー循環の北側の上空には強い西風が形成される。その西風を亜熱帯ジェット気流という。 南半球の亜熱帯高圧帯とその南側の上空にも、亜熱帯ジェット気流が形成される。 ロスビー循環の特徴は偏西風である。日本も偏西風帯にあるが、地上にいると、西寄りの風がふいていることはわからない。 地面付近の風が弱いからである。
しかし、上層雲の動きを注意して観察すると、いつも東向きになっていることに気がつくだろう。 上空にいくにしたがって偏西風は強くなる。対流圏の上部で風速は最大になり、成層圏では高さとともにしだいに弱くなる。 とくに偏西風が強い部分をジェット気流という。
亜熱帯ジェット気流と区別するために、寒帯前線ジェット気流ということもある。 季節によって風速は変化するが、冬季には、日本上空の風速が100m/秒程度になることもまれではない。
偏西風はたえず南北に蛇行しており、この蛇行に対応して、高気圧や低気圧の渦巻が形成される。 新聞に掲載されている地上天気図をみると、直径3000km程度の高気圧や前線をともなった低気圧がかかれているが これらの気圧配置は偏西風にともなう渦巻をあらわしている。 高気圧圏内は弱い下降気流があり、雲が発生しにくいので天気がよい。低気圧圏内は弱い上昇気流があり、雲が発生しやすい。 とくに前線の付近では、地面付近の空気がもちあげられて雲が発生し、それが発達して雨や雪をふらせる。 天気の変化は、高気圧や低気圧の渦巻と密接に関連しているわけである。 これらの渦巻は、1日に1000km程度西から東に移動するので、それに応じて天気も西から東に移動する。
大規模な風系としては、偏西風や貿易風とならんで季節風があげられる。 季節風は、夏と冬で反対向きにふく風である。大陸の地上付近の気温の季節変化は、海洋上の気温の季節変化より大きい。 そのために夏は、海上から比較的すずしい風が大陸にむけてふく。 冬になると、その反対に、内陸部のつめたい風が海洋上にふきつける。 日本は、ユーラシア大陸の東の縁にあるので、このような季節風の影響が大きい。 とくに、冬季にはシベリアからつめたい北西の季節風が日本列島にふきつけ、日本海側の各地に大量の降雪をもたらす。 インドでは、夏季にインド洋からしめった風がふきつけ、インド内陸部に多量の降雨をもらたす。 そのため、季節風をあらわすモンスーンという言葉は、インドでは、雨季の代名詞になっている。
気団と前線
亜熱帯高圧帯は、大陸と海洋の分布が存在するため、地球をとりまく帯にならずに、太平洋上と大西洋上に、とじた等圧線を えがく高気圧として存在する。
北半球では、それぞれ北太平洋高気圧、北大西洋高気圧という。 北半球の高気圧圏内では、空気が時計方向に回転する大きな渦巻になっており、高気圧圏内の大気の性質(気温や湿度)が 比較的均一になる。このように、ひろい範囲にわたって大気の性質が均一になった範囲を気団という。 北太平洋上の気団を北太平洋気団という。北太平洋気団の空気は高温でしめっている 盛夏になると、北海道をのぞく日本の各地は、この気団におおわれるのでむしあつくなる。 反対に冬季には、シベリアに-60ーC程度の非常に低温のシベリア気団(シベリア高気圧)が形成される。 この高気圧からふきだす風が日本に寒波をもたらす。 一般に高緯度には低温の気団が、低緯度には高温の気団が形成され、それぞれ、極気団、熱帯気団と呼ばれる。 2つの気団は中緯度で接しているわけだが、大気はつねに南北方向にうごいているので、2つの気団がぶつかりあう場所が生じる。 このような場所を前線(フロント)という。
前線の付近では、温度が急変するばかりでなく、等圧線がこみあうので、強い風がふくことが多い。 また、冷たい空気の上にあたたかい空気がのりあげて上昇気流が生じ、その中で雲が発生するので、天気がわるくなる。 東アジアでは、初夏にこのような前線が停滞し、1カ月程度の期間、雨がよくふる日がつづく。 その前線を梅雨前線という。梅雨前線にそって、直径1000km程度の小型の低気圧が次々に発生し、西から東に移動する。 1920年ごろにノルウェーの気象学者は、前線が低気圧発生の原因ではないかと考え、低気圧の研究をおこなった。 現在では、低気圧が発生した結果、寒冷前線や温暖前線ができると考えられているが、梅雨前線の場合は、ノルウェーの 学者の考えたように、気候学的な前線にそって低気圧が生まれることがわかっている。
天気予報と気象
第2次世界大戦以降の技術革新、とくに人工衛星、コンピューター、通信手段のおどろくべき発展によって、天気予報の 方法は急速に変化した。
現在でも、天気予報の技術に関する研究は精力的におこなわれており、今後10年の間にさらに 進歩することが期待される。 気象観測データの集計 現在の天気予報は数値予報によっておこなわれる。 数値予報では、現在の大気の状態を知って、それをもとに将来の天気を予測する。 したがって、気象観測をおこなって、現在の大気の状態を知ることは、天気予報にとってかくことのできない作業である。
それも、地球全体の大気の状態を知る必要であるから、国際的なとりきめによって気象観測は世界じゅうでいっせいに おこなわれる。つまりグリニジ平均時の0時(日本時間の午前9時)と12時(午後9時)にいっせいにレーウィンゾンデを放球し 上空の大気の状態を測定する。 このようにしてえられた気象データは、数字の列からなる気象電報の形にして世界じゅうにおくられる。 日本では、東京にある気象庁におくられてくる。それらの数字の列は、すぐにコンピューターにとりこまれて、数値予報に つかわれるだけでなく、気象庁から全国の気象台に配信される。
現在では、これらの作業はすべてコンピューターがおこなっている。 そのシステムをADESS(アデス)といい、Automatic Data Editing and Switching Systemの頭文字をとったものである。 気象データの中には、ゾンデの観測結果ばかりでなく、アメダスによる地上気象観測のデータ、気象衛星の雲画像 レーダーによる降水の分布の資料、気象ロケットによる高度約60kmまでの高層気象観測データなどもふくまれる。
天気予報の種類
1995年(平成7)から気象予報士という国家資格が制定され、気象予報士の資格があれば、事業所を設立しておおやけに天気予報 (短期予報)をおこなうことができるようになった。
それに必要な大量の情報は気象庁から提供される。 気象庁は日本の天気予報事業の中枢である。気象観測をおこなうとともに世界じゅうの気象観測データをあつめ、整理し、全国 の気象官署に配信する。また、さまざまな天気予報をおこなっている 気象庁のおこなう天気予報は、短時間予報、短期予報、週間予報、長期予報に分類される。
普通の天気予報は短期予報といい 2日後までの予報をさす。気象庁は、96年3月から数値予報の計算精度を向上させるとともに、大幅に短期予報の方式を変更した。 新しい短期予報では、従来の天気予報にくわえて、気象要素の分布や時間変化の予報もおこなわれる。 降水の予報は、従来通り確率であらわす(降水確率予報)。 短時間予報は、3時間先までの降水の予報をおこなうもので、レーダーやアメダスの観測結果をもとにしておこなう。 週間予報や1カ月予報は、短期予報と同じように数値予報をもとにしておこなう。 これに対して、3カ月予報(毎月20日発表)、暖候期予報(3月10日発表)、寒候期予報(10月20日発表)は統計的な方法でおこなう。
このような定期的な天気予報にくわえて、気象庁はさまざまな注意報や警報を発令する。 テレビ局や新聞社は、気象庁の発表をもとにして、それに独自の視点をくわえて、バラエティーにとんだ内容の天気予報を 作成している。
数値予報の方法
現在の大気の状態のすべてがわかっていると、物理法則をもちいて、大気の各部分の気温、風速、気圧、湿度などの変化率 (短い時間の間の変化量)を計算することができる。その変化率をもとに、短時間たったあとの大気の状態を知ることができる。 その状態を現在の状態であると想定して、さらに計算をすすめれば、さらにもう少し先の状態を知ることができる。 このような計算をくりかえすと、将来の大気の状態が計算できる。このような原理でおこなう天気予報を数値予報という。
リチャードソンによって提案された数値予報は、当時は実用にならなかった。 数値予報には膨大な計算量が必要なので、計算時間に手間どると、明日の予報の計算がおわる前に翌日になってしまうからである。 しかし、第2次世界大戦後、コンピューターのいちじるしい進歩によって、数値予報が実用化された。 現在は、各国で数値予報によって天気予報がおこなわれている。
気象庁では、1996年3月から新しい方式の数値予報を導入し、地球全体の大気循環と東アジア領域の大気循環の予報を おこなっている。東アジア領域の計算は、水平方向に20kmの間隔で計算する。鉛直方向には36層の大気層を区別してあつかう。 時間的には10分間隔で次々に先の大気の状態をもとめる。
局地予報と確率予報
短期予報は水平方向に20kmの分解能でおこなわれる。
これは従来の数値予報の予報精度にくらべれば、おどろくほど細かい 計算をおこなうモデルであるが、日本のように山の多い国では、20kmでも目があらすぎるほど地形がいりくんだ場所があり 風向きや霧の発生などはそれらの地形の影響をうけ、コンピューターによる計算結果だけでは予報できないことがある。
そこで、数値予報の結果をもとに、さらに地形などの細かい条件を加味していっそうきめ細かい天気予報をおこなうことが のぞまれる。 札幌、仙台、東京、大阪、福岡の5カ所と沖縄の管区気象台や、それぞれの管区気象台に属する地方気象台では、数値予報 の結果をもとにして、その地方独特の天気の特徴を加味した天気予報をおこなっている。
また、民間の気象サービス会社でも、気象予報士が予報の目的にそった局地予報をおこなっている。 しかし、ある場所に雨や雪などがふるかどうかを確実に予報するのはたいへんむずかしい。
現在では、過去の経験をもとに、確率的な考え方を導入して降水の予報をおこなっている。 発表は降水確率をパーセントであらわしているが、予報にしたがって対応し、そなえをするかどうかは そなえに必要な費用と、そなえをしなかった場合にこうむる損害額とのかねあいできまる。 たとえば、大都市に雪がふると、交通網の麻痺などの大きな支障が生じる。 そのような場合は、確率がたとえ20%程度でも、行政機関は雪に対応する準備をしておいたほうがよい場合もある。
降水確率の基準は 降水確率の何%というのはどういう基準で出しているのですか。
気象庁によりますと、各観測点について、コンピューターで向こう24時間(6時間ごと)と1週間(1日ごと)の大気の状態を予測します。これに過去の気象・降水データをあてはめ、雨や雪が降る確率をはじきだします。各地域の確率は、観測点の平均値です。 この確率は1ミリ以上の雨が100回のうち何回降るかを示すものです。1ミリの雨とは「乾いていたアスファルト道路がぬれて、くぼみに水がたまり、傘なしで歩くとかなりぬれてしまう」量です。降水確率は雨の強さや量を表すものではなく、降る時間の長さとも関係ありません。6時間降り続けて1ミリになる場合と、初めの1時間で1ミリの雨が降り、あと5時間は晴れる場合も区別されません。
予報精度
気象観測データをもとにして想定した大気の状態は、観測誤差をある程度ふくんでいるとはいえ、もっとも実際に近い 大気の状態をあらわしている。
しかし、そのような初期状態を設定して、数値予報の計算を先にすすめると、計算に よって予想された大気の状態は、実際の大気の状態としだいにことなった状態になっていく。 一度、実際の大気の状態とずれてしまうと、ふたたび実際の大気状態に近づくということはなくなってしまう。 つまり先を予報するにつれて、実際の大気の状態からのずれはますます大きくなっていく。
現在の技術では、3日先まで予報すると予報精度は83%程度になる。4日先で70%、5日先で60%まで精度がさがってしまう。
したがって、たとえ数値計算によって将来の大気の状態が予想できたとしても、明日の天気を予報するのと同じ確率で 1週間先の天気を予報できるわけではない。この点は、日食や彗星の接近などの天文現象の予測とはことなる。 同じように物理法則にもとづく予測でも、天文現象ははるか将来まで正確に予測できるが、天気は数日間で実際とのくい ちがいがめだってくる。
なぜこのようなちがいが生じるのだろうか。 それは、天体が真空の宇宙空間をほとんど孤立して運動しているのに対して、大気はひろがりをもって地球全体をおおっている つまり満員電車の乗客のように、たがいが影響をあたえながらうごくためである。 このような場合には、計算の出発点で存在したわずかの誤差が、時間の経過とともに急速に大きくなり、全体に影響をあたえて 時間がたつにしたがって実際の大気の状態とのちがいが大きくなってくるのである。
雲物理学と人工気象 雲は、大気中で水蒸気が凝結して、微小な水滴や氷晶(小さな氷の結晶)になったものである。 それらの雲の粒は水蒸気をあつめて成長したり、たがいにくっつきあって大きな雨粒や雪片になって地上におちてくる。 このように、大気中の水が氷になったりするような、相変化に関係した物理現象を研究する学問を雲物理学という。
雲粒の成長や雨、雪、霰(あられ)、雹など降水粒子の形成過程は大変複雑な現象で、まだよくわかっていないことも多い。 すべての雲から雨や雪がふってくるわけではない。雲粒が雨粒になるには、特別な条件が必要なのである。
気温が0ーCより低い状態でも、小さな水滴のままでいることがある。このような現象を過冷却という。 過冷却状態の水滴の中に、さらに上空から小さな氷晶がふってくると、氷晶が急速に成長して雪の結晶になることが 知られている。地面付近の気温が2ーCより高いと、空中で雪がとけて雨になる。気温がそれより低いと雪になることが多い。 このような仕組みでふる雨を「つめたい雨」という。
人工降雨は、この性質を利用して人工的に雨をふらせようとする技術である。 過冷却状態の水滴だけでは雪に成長しないが、その中に人工的に氷晶をつくれば、それが成長して雪になることが考えられる。 そこで、過冷却状態の水滴からできている雲の中にドライアイスをまく方法が考案された。 ドライアイスは非常に低温なので、そのまわりの空気がひやされ、その中の過冷却状態の水滴が凍結する。 すると、それが急速に成長して雪になる可能性がある。 もうひとつの方法は、ヨウ化銀の小さな結晶を過冷却状態の雲におくりこむことである。 ヨウ化銀の結晶の分子配列の間隔は、氷の結晶の分子配列の間隔と似ているため、ヨウ化銀は過冷却水滴に接触すると 氷に接触したときと同じように凝結する。
この性質をつかって、人工的に雨をふらせる実験が数多くおこなわれた。 しかし、このような方法が本当に有効かどうか判定することは大変むずかしい。 もともと雨がふりそうな状態の雲にドライアイスやヨウ化銀をまくのだから、あるいはそんなことをしなくても雨がふる 可能性もある。そこで、人工降雨の有効性の判定は統計的な方法でおこなわれることが多い。 たとえば偶数日だけ1年間以上実験をつづけ、奇数日はおこなわない。 1年後に偶数日と奇数日で降雨量に有意な差が生じるかどうか、統計的にたしかめるというような方法である。 しかし、雨は毎日ふるわけではないので、このような統計的方法によっても、人工降雨の効果を実証することはなかなか 困難である。
ハワイなどの熱帯地域では、雲頂の気温が0ーCより高くても雨がふってくることがある。 このような雨を「あたたかい雨」という。雲の中の気温は0ーCより高いから、氷晶が発生することはない。 海上の大気中には、波しぶきが蒸発したあとに海塩核という小さな塩の結晶が空気中にのこされる。 それが上空にはこばれると、海塩核のまわりに水蒸気が凝結して他の雲粒より大きな雲粒ができる 大きな雲粒は落下する速度がはやいので、まわりにうかんでいる小さな雲粒とぶつかり、ますます大きくなって雨粒になると 考えられている。
雲 くも Cloud
大気中で、水蒸気が水にかわる凝結という現象がおこり、これによってできた細かい水滴や微小な 氷晶(氷の結晶)が上空にうかんでいる状態。 水蒸気は地表から蒸発し、上空へはこばれ、凝結して雲となり、そしてまた降水として地表に もどってくる。 これを水循環とよんでいるが、雲はこの地球上の水循環でのひじょうに重要な一段階である。 また、雲は目にみえる主要な大気中の現象である。
雲の形成と影響
空気が冷却されると、目にみえない水蒸気が凝結して、目にみえる雲粒あるいは氷の粒子になる。
雲粒の大きさは、約0.0005〜0.0075cmである。これらの粒はひじょうに小さく、わずかな上昇流に のって容易に空中にうかんでいることができる。
雲の組成の違いは凝結のおきる温度の違いによる。 通常、凝結が凝固点以下でおきると、雲は氷晶からなり、よりあたたかい空気中でできると水滴から なる。しかし、ときおり凝固点以下で水滴をふくむ過冷却の雲ができることがある。 雲が発達していくときの空気の動きは雲の形に影響をあたえる。 静穏な空気中で発達した雲はシート状あるいは層状になり、強い垂直気流の中でできたものは背の 高い雲になる。
雲は太陽からの熱を、地表面と大気へ分配するのに重要な役割をはたす。 一般に、雲頂での反射は地表での反射よりも大きいので、曇りの日のほうが、反射され宇宙空間に もどされる太陽エネルギーの量は大きい。 ほとんどの太陽の放射は雲層上部で反射されるが、一部は地上まで到達する。 地表はこのエネルギーを吸収し、再放射する。雲層下部は長い波長の地球放射をとおさず、地表に むけてまた反射する。
このように、放射エネルギーが外へにげにくくなるので、一般に、曇りの日には下層の大気は 放射熱エネルギーをよけいに吸収する。 それに対して、晴れの日は、より多くの太陽放射がいったん地面に吸収されるが、雲がないので このエネルギーは、ふたたび放射されてどんどん大気外へにげていく。 実際、他の気象要素を考えなければ、晴れの日は曇りの日より放射の吸収が小さい。
雲は人間の活動に大きな影響をおよぼす。たとえば、雲からもたらされる雨は、農業にとって ひじょうに大切なものである。
また、初期の航空機にとって、雲の中の飛行は、視界をさまたげられるため、困難をきわめた。 今日では計器飛行が発達し、あつい雲の中でも飛行機を操縦することができる。 さらに、曇りの日の照明のための電力消費の急激な増加は電力産業が直面する大きな問題である。 雲の科学的研究は、1803年にイギリスの気象学者ルーク・ハワードによる雲の分類にはじまり 後の国際雲級図(1896)へと発展した。 これは、その後かなり改訂され(最近では1956年)、現在では世界じゅうでつかわれている。
雲の分類
雲は、地面からの高さによって、ふつう4つのグループにわけられる。 上層雲、中層雲、下層雲、そして垂直方向に発達し多くの層にわたっているものである。 これらは、さらにその形とでき方により、類、種、変種にわけられる。100種類以上の雲がある。 以下に4つのグループとおもな類について説明する。
上層雲
氷晶からできていて、平均高度は8km以上である。 巻雲(けんうん)、巻層雲、巻積雲の3つの類にわけられる。
巻雲は、はなればなれの白くて細い雲で、羽毛状、すじ状、または房をともなった帯状などにならぶ。 「すじ雲」ともよばれる。
巻層雲は幕状で、きめの細かい白っぽいベールのようにみえ、全天あるいはかなりの部分をおおう。 太陽や月との間にかかるとその周囲に「かさ」の現象がみられる。 「うす雲」ともよばれる。
巻積雲は小さな白い羊毛状の塊で、列状などに規則的にならんでいることが多い。 「いわし雲」「うろこ雲」などとよばれる。
中層雲
水滴からなり、高度は約3〜6kmにある。高層雲、高積雲、乱層雲の3つの類がある。
高層雲はあつく、灰色または青みをおびたベールのような雲で、太陽や月は曇りガラスごしに みるようにぼんやりとみえるが輪郭がはっきりしない。 「おぼろ雲」ともよばれる。
高積雲は、巻積雲よりいくぶん大きな密集した羊毛玉状になる。 太陽や月との間にかかると、その周囲に光冠がみられることがある。 この直径はかさの直径よりずっと小さい。「ひつじ雲」「むら雲」などとよばれる。
乱層雲は中層を中心に、下層や上層におよぶこともある。 しかし、対流性の雲ではなく層状性の雲なので、中層雲のグループにいれられる。 あつく黒い雲で、きまった形はない。これは雨雲で、原則として雨か雪をふらせる。
下層雲
これも水滴からなるが、一般にその高度は2kmより低い。 層積雲、層雲の2つの類がある。
層積雲はいくつもの大きなうね状の雲で、やわらかそうで 灰色をしている。全天をおおうことがよくある。 ふつうはそれほどあつくならないので雲の切れ目から青空がみえることがある。 「うね雲」ともよばれる。
層雲は平らにひろがった高い霧で、白、または灰色の毛布のようにみえる。 通常約600mより低い。 あたたかい上昇気流によって切れ目ができると、その向こうの空は真っ青なことが多い。 「きり雲」ともよばれる。
垂直に発達した雲
この種の雲は、雲底は高度2kmより低く、雲頂は数kmになり、積乱雲では13kmより高くまで およぶものもある。 積雲と積乱雲の2種類にわかれる。
積雲はドーム型で綿のような雲である。 昼から午後にみられることが多く、このときは太陽の加熱で、この雲の生成に必要な垂直気流が おきている。通常、雲底は平らで、雲頂は丸みをおびたカリフラワー状である。
積乱雲は黒く重量感のある雲で、大気中に山のようにそびえ、発達したものは雲頂付近でひろがる。 このひろがった部分を「かなとこ雲」とよぶ。 積乱雲は入道雲の名で知られ、ふつう、突然のはげしいにわか雨をともなう。
変則的だがひじょうにうつくしい雲の仲間に、真珠雲(真珠母雲)と夜光雲がある。 高度はそれぞれ、約20〜30kmと約50〜55kmである。これらの雲はひじょうにうすく、高緯度地方の 日没から日の出までの間だけしかみられない。 航空機が高いところをとぶようになり、人工的な飛行機雲がみられるようになった。 これは飛行機のエンジンの排気ガスにふくまれる水蒸気が凝結したものである。
液体 えきたい Liquid
気体と固体の中間に位置する物質の状態。
液体の分子は固体の分子ほど密につまっておらず、気体の分子ほど配列がばらばらでもない。 液体のX線研究の結果、分子数個分の大きさで、一定の分子の規則性が存在していることが わかっている。 いくつかの液体では分子が向きやすい方向をもっているものもあり、屈折率のような性質が 軸によってことなる 異方性をしめす。
適当な温度と圧力の条件下において、ほとんどの物質は液体状態で存在することができる。 しかし、昇華して、固体から直接気体になる固体もある。 液体の密度は、ふつうは同じ物質の固体状態の密度よりも低いが、それほどちがわない。 水のように液体の密度のほうが固体の氷の状態よりも高い物質もある。 液体には粘性とよばれる、流れに対する抵抗がある。液体の粘性は温度が低くなると下がり 圧力がますと上がる。 粘性は液体を構成する分子の複雑さにも関係している。 たとえば液化不活性ガスの粘性は低く、重油の粘性は高い。 液体と平衡状態にある蒸気の圧力は蒸気圧とよばれ、温度によってきまり、それぞれの液体に 固有な値をしめす。
沸点、凝固点、気化熱(液体を蒸気にかえるのに必要な熱量)も、それぞれの液体できまっている。 ときに液体は、沸点よりも高い温度に熱することができる。この状態を過熱という。 同様に、液体は凝固点以下に冷却されることがあり、これを過冷却という。
湿度 しつど Humidity
大気にふくまれている水分量。大気はいつでも水蒸気をふくんでいるが、空気にふくまれる水蒸気量には、気温によってきまる最大値があり、飽和水蒸気量とよばれている。
飽和水蒸気量は温度があがるとふえる。1kgの空気は、地上付近ではおおよそ約1m3の体積を占めているが、0ーCでは最大で4.8g、37ーCでは39gの水蒸気をふくむことができる。空気が水蒸気で飽和していると、汗をかいても蒸発せずすずしく感じないので、ひじょうに不快である。
一定の体積中の水蒸気の重さを絶対湿度といい、1m3中の水蒸気の質量をグラムであらわしたものをつかう。天気予報でもちいられる相対湿度は、大気中に実際にふくまれる水蒸気量と、同じ温度で飽和している空気にふくまれる水蒸気量の比(%)であらわす。
温度が高くなっても、水蒸気の量がかわらなければ絶対湿度は変化しないが、相対湿度は低くなる。気温がさがれば相対湿度はあがる(→ 露)。湿度は湿度計ではかる。
温度が高いとき、人が感じる不快感、とくに蒸し暑さをあらわすものとして不快指数が考案された。これは、乾球温度と湿球温度をセルシウス度であらわしたものの和に0.72を掛け40.6を足して計算する。
たとえば、乾球温度が32ーCで湿球温度が23ーCならば不快指数80強、同じ乾球温度で湿球温度が30ーC ならば85になる。日本人の場合、指数75〜84では半分の人が不快と感じ、85ではほとんどの人が不快と感じるといわれている。
| テーマ館目次 |